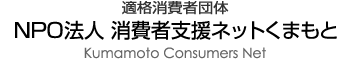活動状況
消費者法ニュース第142号に当法人理事長が寄稿しました
(消費者法ニュース143号原稿)
適格消費者団体NPO法人消費者支援ネットくまもと 活動報告(令和6年11月)
当法人は、毎年、熊本県議会に対して「地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・充実を求める意見書」の提出を求める請願を行っており、熊本県議会から毎年意見書を提出いただいている。
実際のところ、消費生活相談件数は全国で約90万件であるが、消費生活センター等に相談している人は消費者被害に遭った人の1割にも満たないという国の調査結果があり、多くの国民が実際に消費者被害に遭っている現状がある。どうすれば消費者被害を減らすことができるのか。
地方公共団体の消費生活相談体制をより充実させればより多くの消費者被害の救済ができるようになると思われる。しかしながら、現在地方消費者行政で消費生活相談員の人件費に活用されている交付金のメニューが、令和6年度~令和7年度末で多くの公共団体で活用期限を迎える。熊本県内でも、令和6年度末で3自治体が、令和7年度末で9自治体が終了となる。この課題により、その行政分野が地方公共団体の中で確立しているとは言えない地方消費者行政がさらに衰退するおそれがある。そのことは、地方支分局を持たない消費者庁が行う施策にも影響を与えることが予測される。
地方消費者行政を取り巻く課題はさらにある。地方消費者行政と両輪で消費者被害の未然防止、拡大防止を行っている適格消費者団体に対して地方消費者行政が行っている予算措置(委託、補助)の財源となっている交付金のメニューも、多くの公共団体で令和7年度に終了を迎える。このことは、適格消費者団体の活動に大きな影響を与えることになり、やはり、消費者庁が行う施策にも影響を与えることが予測される。
消費者行政は従前から、国、都道府県、市区町村の三層構造といわれてきた。さらに、適格消費者団体が行政と両輪で消費者保護の未然防止・拡大防止の公益的機能を持ち、行政機関と適格消費者団体の有機的連携が現在の実質的な消費者行政を形作っている。
そのような状況下、消費者庁は、地方消費者行政を含む消費者行政をどのようにしていきたいと思っているのか。消費者庁を最も観察し報道してきている、日本消費経済新聞の相川記者から、ここ数年の消費者庁の動き、消費者庁の地方消費者行政を含めた消費者行政施策の経過、現状、課題等についての報告を受け、参加者全員で共通認識を持つ。そのうえで、地方消費者行政を含めた消費者行政推進のために、あるいは後退させないために、私たちができることについて、シンポジウムで協議を行う。
熊本県弁護士会、ネットくまもとでは、国民生活の安定の基礎を担っている地方消費者行政を安定的に推進させるために国が交付金等の財政措置を継続的に講ずるよう、国会及び政府に対して意見書を提出していただくことをお願いする請願を毎年度県議会に対して行うとともにその全国展開を呼びかけているが、さらに私たちができることについて、パネラーの話し合いを通して、参加者全員で考える会としたい。